  |
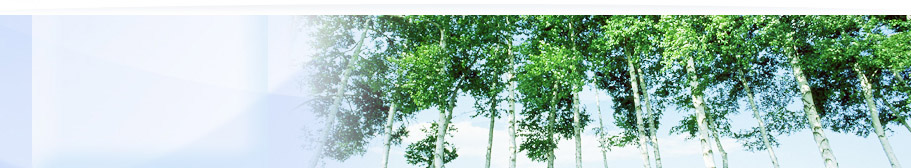
  |
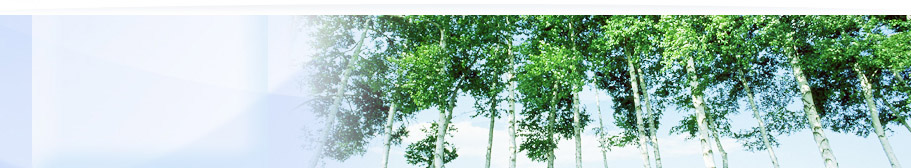
現場でのサンプリング作業、地点打合せ等に対応可能です。
現場では通称で残土とも言われ、搬出先によりサンプリング方法、分析項目等が異なり写真撮影にも細かく指定されている事もあります。
首都圏の自治体では、建設工事に伴い発生する土砂等の埋立て処分、盛り土やたい積等を行う場合には、受け入れ基準を定め、 その基準に適合するものを受け入れる様、条例で定めています。
当社では、土壌試料の採取・ご報告までを 短納期で対応しております。
搬出先さえ指定して頂ければその搬出先に応じた現地作業をさせて頂きます。
私共は翌日に対するご依頼でも承りますので、お気軽にご連絡下さい。
各自治体において、土砂の堆積、埋立て等による土壌汚染の防止を図る条例が制定されている条例です。
(通称、残土条例)
ご連絡頂ければ、条例内容に沿った調査をご提案させていただきます。
建設残土が発生しましたら、土壌分析を行います。
千葉 / UCR / 横浜公社 / 東京に合わせた採取を行います。




Q:残土の搬出を検討しているが、分析の頻度と項目は何が必要ですか?
A:搬出先の仕様により異なります。千葉県及び栃木県条例では搬出土量5,000m3に1回、溶出試験26項目+含有試験2項目の検査が必要です。茨城県条例では搬出土量3,000m2に1回、溶出試験26項目+含有試験2項目の検査が必要です。その他、UCRや民間の受入れ先では個別に仕様がございますので、お手数ですが、詳細は受入れ先にご確認ください。
Q:試料の採り方と必要な試料量は?
A:搬出先の仕様により異なることがありますが、原則として、5地点混合方式での採取を行い、合計500g程度の試料が必要です。5地点混合方式での試料採取は、現場の対象区が広い場合では、中心を1地点決め、そこから東西南北に5〜10m間隔で4地点の計5地点から採取します。現場の対象区が長い場合では、直線上に5〜10m間隔で5地点から採取します。
Q.分析方法(採取方法)が違うと言われましたがどうしたら良いですか?
A.土壌の環境基準の分析方法を受入基準としている受け入れ先が多いです。しかしまれに産業廃棄物中の有害物質の分析方法を採用している場合がございます。
この場合、分析項目が同じでも改めて受入先の要綱に沿った分析を行う必要があります。なお、受け入れ先によっては、試料の採取方法等も詳細に取り決めている場合がございます。
Q.土壌改良剤の影響はありますか?
A.六価クロム等の重金属類が溶出しやすくなる場合がございます。
そのほか関東近郊で1,000件以上